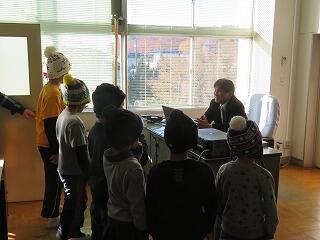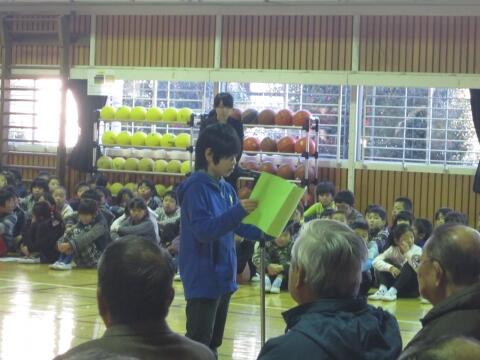今日は、ひかり学級の友達がスケート教室に参加しました。市内各校の友達と一緒の「スケート教室」で、たくさんの友達と一緒の楽しい体験になりました。
まずは、学校の先生方に「行ってきます」のごあいさつ。
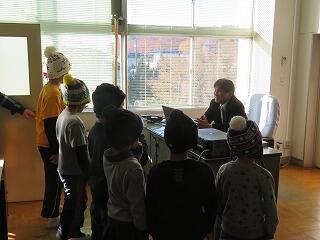
「校長先生。行ってきます!」

「保健室の先生。行ってきます!」

「1年生の先生。行ってきます!」

バスに乗ります。他の学校の友達にも「おはようございます」のあいさつができました。

会場に着いたら、準備体操。

スケートシューズを持って、いよいよ始まるね。

まずは、カラーコーンを支えに長靴を履いて、氷の上へ。「簡単簡単・・・」と思っていると

「うわっ!」

「おしりが痛いよ~。冷たいよ~。先生助けて~」と言われても、先生も滑れないので・・・「頑張れ」としか言えません。

氷の上で悪戦中のみんなとは別に、スイスイ滑っているMさん。とても上手に滑っていますね。

さぁて。次は、いよいよスケートシューズを履いて挑戦・・・?

おっとととと。「こんなクツじゃ歩けないよ~」「重いよ~」「足がカクカクするよ~」「ペンギン歩きって何?」リンクサイドで悪戦苦闘。さらに、氷の上では・・

壁から手が離せません。

「戻りたいよ~」「助けて~」と言いながらも、リンクに入ってしまったら、戻れない。がんばって1周回って(滑って?)きました。

楽しい体験はあっという間でしたね。運動の後は、水分補給。

「ありがとうございました」大きな声でお礼のあいさつ。

バスが待つ場所まで歩くのですが、「足が重い」とつぶやく友達もいましたね。滑っていた感覚が足に残っているから、何か変な感じがしましたね。

疲れた表情のみんなでしたが、学校に戻ると元気復活。給食をモリモリ食べて午後の活動もがんばりました。