文字
背景
行間
学校生活の様子をお知らせします。
4月10日 満開の桜の花の下で…
きょう,令和6年度の入学式が行われました。天候に恵まれ,満開の桜をバックに新入生の写真を撮る保護者さんの姿もたくさん見られました。元気いっぱいの1年生を迎え,明日から全校児童そろっての登校となります。みんな仲良く元気に頑張りましょう!
さて,昼休みには,陽射しがたっぷりと注ぐ校庭に子供たちの姿がたくさん見られました。「先生,桜の花,きれいですね。」「きれいな花びらを拾いました!」「この前,お花見に行ったんです。」と子供たちが話しかけてくれます。陽射しだけでなく,目に映る淡いピンク色の情景にもあたたかさを感じます。子供たちも,ドッジボールに鬼ごっこ,ブランコ,一輪車など,思い思いに休み時間を楽しんでいました。




4月9日 明日は入学式!
入学式の準備が整いました。6年生の子供たちが進んで仕事を見付け作業をしてくれたので,式場や1年生の教室など,滞りなく準備が整いました。「ハイ!」「何か手伝うことはありますか?」「私,こっちやるね。」「よし,ここをきれいにしよう」と気持ちのよい返事や前向きに取り組もうとする言葉が聞こえてきます。とても気持ちがいいです。6年生には,入学式当日も,1年生と手をつないで席まで一緒に歩く役目をお願いしています。1年生との対面を楽しみながら笑顔で頑張ってほしいです。






4月8日 着任式・始業式
令和6年度のスタートです。新しく着任された先生方をお迎えし,1学期の始業式を行いました。子供たちはやや緊張した面持ちで式に臨んでいます。そして,元気に挨拶をし,しっかりとした態度で話を聴くことができました。
「やさしく かしこく たくましく」この合言葉を念頭に,子供たちは今年も多くのことを学び,成長していくことでしょう。子供たちの笑顔がたくさん見られるよう,そして,一人一人が充実した学校生活を送れるよう支援していきたいと思います。






4月5日 新学期に向けて
先生が集まって研修を進めています。新学期,子供たちを迎えて「どんな学級をつくっていこうか」と,児童指導主任が声を掛けて話合いの時間をもちました。年度の初めには,学級目標を話し合ったり係活動を考えたりしますが,子供たち一人一人が自分の学級を好きになって,一人一人が学級の成熟に役割を果たせるように子供の力を高めていきたいものです。先生たちは,そのきっかけを作ったり,子供たちを見守ったり支援したりしながら,子供と一緒に歩んでいきます。
児童の皆さん,もうすぐ新学期が始まります。元気に登校してきてくださいね。

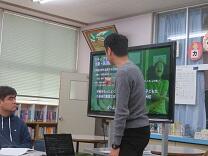
3月31日 花開きました!
きのうから気温が上がり,全国各地から開花のたよりが届いています。
明日から新年度が始まりますが,それを待っていたかのように校庭の桜も花びらが開き始めました。豊郷南小学校の児童の皆さん,春休み,元気に過ごしていますか?
始業式には,きっと満開の桜が皆さんを迎えてくれることでしょう。























