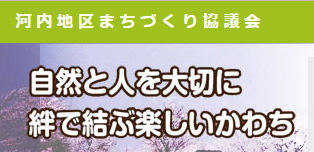本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。
文字
背景
行間
日々の様子
アクセス数
3
6
4
9
4
7
6
祝 2,700,000アクセス達成! ありがとうございます。 令和6.11.6
祝 3,000,000アクセス達成! ありがとうございます。 令和7.3.3
祝 3,500,000アクセス達成! ありがとうございます。 令和7.11.10
保健室から
インフルエンザ経過報告書
・インフルエンザ経過報告書.pdf
・【記入例】インフルエンザ経過報告書.pdf
マイコプラズマ肺炎等治療後の登校届
登園・登校届(両面) (1).pdf
スポーツ振興センター申請書類
・医療等の状況 別紙3(1)病院、診療所、歯科医院【R1~】.pdf
・医療等の状況 別紙3(3)柔道整復師用【R1~】.pdf
・調剤報酬明細書 別紙3(7)薬局(病院外の調剤薬局)【R1~】.pdf
ケータイ・スマホ宮っ子ルール宣言
携帯電話やスマートフォンについて,親子で話し合ってみましょう。
ケータイ・スマホ宮っ子ルール宣言.pdf
(宇都宮市教育委員会より)
古里中学校いじめ防止基本方針.pdf古里中いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針.pdf
いじめから子供を守ろう.pdf
(宇都宮市PTA連合会より)
Stop!いじめ!!.pdf
(県教委河内教育事務所より)