本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。
文字
背景
行間
日誌
あっという間の2週間
3人の教育実習生の内、1名が本日最終日を迎えました。10月13日からの10日間でしたが、貴重な経験を積むことが出来たようです。教育実習生からは、「学校全体が良い雰囲気に包まれていて、生徒みんながとても楽しそうにしていると感じました。最新映画に『心を燃やせ』というキャッチコピーがあるように、熱中できることを見つけて、これからの学校生活を送ってください。」と後輩にエールが贈られました。



F・ART展を開催しています
文化祭中止に伴い美術部の発表の場も失われてしまいました。そこで今年度は、この展覧会を開き、美術部の発表の場にしました。F・ARTはFurusato(古里)ART(芸術)とFine・ART(美術)の2つの意味を掛け合わせた造語です。なお、この展覧会は3年生の卒業制作展も兼ねています。10月26日(月)~11月5日(木)の学校公開日に合わせて開催しています。



図書館司書さんの離任式
平成29年度より本校で勤務している学校図書館司書さんが退職することになり、離任式を行いました。生徒会長からお礼の言葉を伝え、記念品として、花束とクラス毎に趣向を凝らした映像をまとめたDVDが贈られました。岡本北小学校卒業の生徒は8年にも渡り読書の楽しさを教えてもらっています。名残惜しいお別れとなりますが、新天地でも活躍されることを期待しています。



【本日の図書室の様子】


手作りマスクを頂きました
本日、河内地区社会福祉協議会より多くの手作りマスクや市販マスクの贈呈を受けました。このマスクは、同協議会の呼び掛けにより寄付された物です。詳しくは、まちづくり情報紙「かわち」第72号の記事「パンダの回収BOXご協力ありがとうございました」をご覧ください。


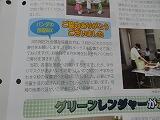
正しい情報を踏まえた進路選択のために
本日、宇都宮工業高校と高根沢高校の先生に来校していただき、高校説明会を実施しました。この説明会は、県立高校の先生から直接説明を聞き、質疑応答をすることにより、生徒および保護者がより詳しい情報を得て進路選択ができることを目的に企画しています。先週は、宇都宮清陵高校、宇都宮白楊高校、宇都宮商業高校の説明会を実施しました。毎回10数人の生徒と保護者が参加し、熱心に話を聞いて、質問をしていました。11月からは3年生の進路相談が始まります。より自分の良さを伸ばすことが出来る高校を選択してほしいと思います。


受験は団体戦!
本日は各学年で朝会を行いました。どの学年も後期の学級委員長の自己紹介を実施し、これからの学級づくりへの抱負を述べました。また、3年生は「受験モードチェックリスト10」を記入することで、受験対策の状況を自己分析しました。3年職員からは、「受験は団体戦」を合言葉に、「受験するのはあくまでも自分自身。人任せにしない。でも大丈夫!君だけじゃない。古中3年生みんなで受験という大きな山に挑んでいこう!」と勇気づける話がありました。

【チェックリストへ記入中】 【3年職員からの話】



タスキは無くとも心を繋いで
本日、宇河地区駅伝競走大会がカンセキスタジアムとちぎにて、男女それぞれ16チームが参加し、タイムトライアル方式で開催されました。男女ともエントリーから外れた選手の激励を秘めて、力走しました。結果は出場した男女11人の内、9人が自己ベストを更新する健闘を見せ、女子は6位入賞、男子は11位の成績でした。今年はタスキを繋ぐ方式ではありませんでしたが、新しいスタジアムで走ることが出来、貴重な経験を積むことができました。



【女子1区】 【女子2区】 【女子3区】



【女子4区】 【女子5区】


【男子1区】 【男子2区】 【男子3区】



【男子4区】 【男子5区】 【男子6区】



宇河地区駅伝競走大会 結果速報
集計の結果 11位となりました。
男子出場選手の全員が自己ベスト更新と健闘しました。
宇河地区駅伝競走大会 結果速報
集計の結果、6位入賞となりました。
(男子は、12:30~ 1区走者が走ります。)
先生も日々勉強です(2)
7/14に続き、第2回「授業実践力養成サポート事業」を実施しました。今回も3年1組の理科の授業において公開授業を行いました。本日の授業は、物理分野「仕事とエネルギー」の単元で、物体の持つエネルギーの大きさと、速さや質量の関係を調べる内容でした。グループ活動では、条件を整えて実験を進め、試行錯誤しながら結果の考察をしていました。講師からの指導講評では、前回からの改善した点と今後の課題についても助言していただきました。




